ネットワーク機器を複数のケーブルで接続すると、帯域が広がったり、片方のケーブルに障害があっても通信を継続できるようになります。その仕組みが「リンクアグリゲーション(LAG)」です。
この記事では、Ciscoスイッチで基本コマンドを扱える方向けに、LAGの基本から設定方法までわかりやすく解説します。
LAGとは?リンクアグリゲーションの概要
リンクアグリゲーション(LAG: Link Aggregation Group)は、複数の物理的なネットワーク回線をまとめて、1本の論理的な回線として扱う技術です。Cisco機器ではこの仕組みを「EtherChannel(イーサチャネル)」と呼びます。
例えば、2本の1Gbpsの回線をLAGで束ねれば、2Gbps相当の通信が可能になります。さらに、どちらか一方のケーブルが障害で切れても、もう一方で通信を継続できるため、高可用性も確保できます。
LAGのメリット
- 帯域幅の拡張:複数リンクを束ねて1つの高速な通信路にできます。
- 冗長性の確保:1本のリンクがダウンしても他のリンクで通信継続。
- STP(スパニングツリー)の制限回避:複数リンクを1つの論理リンクとして扱うため、ポートのブロッキングが発生しない。
- トラフィックの負荷分散:複数の通信を物理リンクに分散し、パフォーマンスを安定化。
静的LAGと動的LAG(LACP)の違い
LAGには2つの構成方式があります。
- 静的LAG:
channel-groupコマンドのモードをonに設定。事前に両端を完全に一致させる必要あり。 - 動的LAG(LACP):IEEE標準のリンク集約プロトコル。Ciscoでは
active/passiveモードで設定。設定ミスの検出や自動調整が可能で推奨。
多くの場合はLACPを使うのがベストです。相手機器がCisco以外の場合でも動作するため、マルチベンダー環境にも適しています。
Ciscoスイッチでの設定例(LACP)
ここでは、GigabitEthernet0/1と0/2をLAG構成して、LACPで動的リンクアグリゲーションを行う設定例を示します。
Switch(config)# interface range GigabitEthernet0/1 - 2
Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode active
Switch(config-if-range)# exit
Switch(config)# interface Port-channel1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
Switch(config-if)# no shutdown
両端のスイッチで同様の設定を行ってください。channel-group番号(上記では「1」)は一致させる必要があります。
状態の確認方法
LAG構成後は、以下のコマンドで状態確認ができます。
Switch# show etherchannel summary「Port-channel1」が SU と表示され、各ポートが P(bundled in port-channel)になっていれば正常です。
LAG使用時の注意点
- メンバーポートは速度、デュプレックス、VLANなどの設定を揃える。
- 両端で同じLAG構成(静的/動的)を使う。
- 一方が
onで他方がactiveだと不整合が起きる。 - 通信の最大速度は1フローあたり物理リンク1本分(例:1Gbps)。合計帯域向上は複数フロー時のみ。
トラブルシュートのポイント
- Poが上がらない:片側の設定が不足していないか確認。
- suspended状態:設定不一致(VLANや速度)を見直す。
- 速度が出ない:複数のセッションで帯域が増える設計。
まとめ
リンクアグリゲーション(LAG)は、ネットワークの冗長性や帯域強化にとても有効な技術です。CiscoスイッチではEtherChannelとして簡単に設定でき、LACPを使えばより安全で柔軟な構成が可能です。この記事の内容をもとに、ぜひLAG構築に挑戦してみてください。
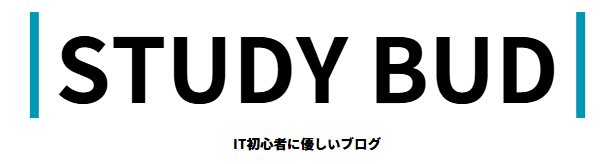


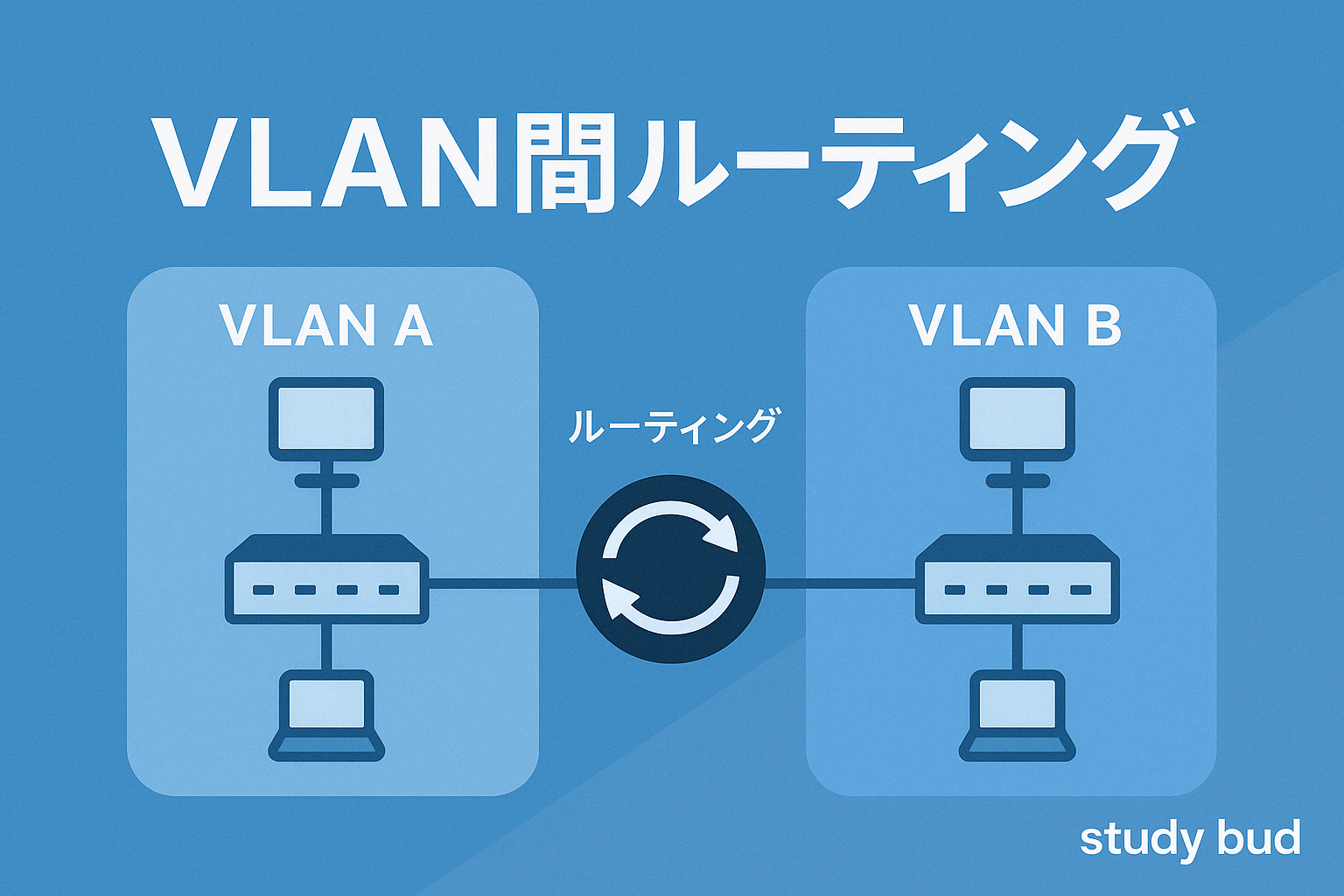
コメント